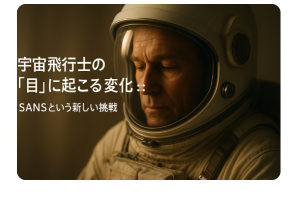 宇宙飛行士の「目」に起こる変化 ― SANSという新しい挑戦
宇宙飛行士の「目」に起こる変化 ― SANSという新しい挑戦
~国際宇宙ステーションのデータから見えた予測の可能性~
◎背景
長期間の宇宙滞在は、私たちの体にさまざまな影響を及ぼします。その中でも注目されているのが「宇宙飛行関連神経眼症候群(Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome:SANS)」です。
これは、国際宇宙ステーション(ISS)で半年以上滞在する宇宙飛行士の約7割に見られるとされる、視神経乳頭(視神経の出口)のむくみや、眼球の形の変化、遠視化などを伴う病態です。
重症例では視力低下や視野変化を起こすため、将来の火星探査などの長期宇宙飛行計画にとって大きな課題となっています。
◎目的
これまで、SANSが誰にどの程度起こるのかを「予測」できる指標はありませんでした。
本研究では、NASA宇宙飛行士の2回以上の長期宇宙滞在データを解析し、
・SANSが再び起こるかどうか
・その重症度を予測できる指標があるか
を調べることを目的としました。
◎方法
研究チームは、2007年から2024年の間に国際宇宙ステーションで2回の長期滞在を行った16人のNASA宇宙飛行士(平均年齢46〜53歳)を対象としました。
全員が滞在前・滞在中・帰還後に**光干渉断層計(OCT)**などの眼科検査を受けており、視神経乳頭浮腫(ODE)の厚みや網膜の構造変化が詳しく記録されています。
それらを遡って解析し、前回の宇宙飛行中にSANSを発症した人が、次の飛行でも再発するかどうかを検討しました。
◎結果
-
16人中約20%が女性、平均滞在期間は約6か月でした。
-
前回の宇宙飛行でSANSを発症した宇宙飛行士は、次回も高確率でSANSを再発していました。
-
感度85.7%、特異度100%、陽性的中率100%という極めて高い一致率でした。
-
-
また、OCTで測定された視神経周囲の網膜厚の変化量(ΔTRT)も、
1回目と2回目でほぼ同じ傾向を示す(相関係数 r=0.94)ことが分かり、
各個人の「SANSになりやすさ」や「むくみの強さ」には再現性があることが示されました。
◎結論
この研究は、過去の宇宙飛行中のデータから次のSANSリスクを予測できることを初めて明らかにしました。
つまり、宇宙飛行士ごとに「SANSのなりやすさ」がある程度決まっており、
次のミッション前にその人に合わせた個別の予防策や訓練、治療準備が可能になるかもしれません。
将来的には、打ち上げ前のOCT検査で得られたデータから、
長期滞在に伴う視機能リスクをあらかじめ予測することが期待されます。
眼科医清澤のコメント
宇宙飛行によって眼に浮腫や形の変化が起きるという報告は、眼科医として非常に興味深いものです。
重力がない環境では、体液が上半身に移動し、頭蓋内圧や視神経周囲の圧力変化が生じると考えられています。
それが「視神経乳頭浮腫」を引き起こす主な原因とされています。
本研究が示したように、OCTによる網膜・視神経計測は、宇宙医学だけでなく地上の医学にも応用できる可能性があります。
例えば、頭蓋内圧の微妙な変化を反映する客観的指標として、緑内障やうっ血乳頭などの評価にもヒントを与えてくれるでしょう。
人類が火星を目指す時代、宇宙飛行士の「視力を守る」ために眼科の技術が果たす役割はますます大きくなっています。
出典
Blanchstetter TJ, Mason SS, Osborne S, et al.
Prediction of Spaceflight-Associated Neuro-ocular Syndrome in International Space Station Astronauts.
JAMA Ophthalmology. Published online October 9, 2025.
doi:10.1001/jamaophthalmol.2025.3406




コメント