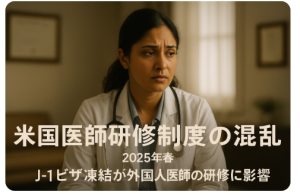
清澤のコメント:我々の世代では海外留学は若手医師のあこがれの対象でしたが、最近の日本人若手医師は米国への留学を比較的に希望しなくなっているようです。それでも、米国の医学界では海外の医学部卒業生は医療の底辺を支える存在として今も必要とされていて、それに対するトランプ政権下でのビザの発給の遅れが社会的な混乱を起こしているという事のようです。医療は国境を越えて支え合う仕組みの上に成り立っています。眼科でも留学経験を持つ医師が多く、国際交流は医学の進歩を促します。米国のビザ混乱は、日本にとっても「医師不足をどう補うか」を考える警鐘といえるでしょう。
記事の要点;2025年春、アメリカでは医師研修制度に大きな混乱が起きました。原因は、外国出身の医師が研修に参加するために必要な「J-1ビザ」の発給手続きが一時的に凍結されたことです。これにより、すでに研修先が決まっていた多くの国際医学卒業生(IMG: International Medical Graduates)が、研修開始日に間に合わず、全米の病院で業務に支障が出ました。
この問題は、医師会など複数の団体の働きかけで解決しましたが、「外国人医師に依存する体制は不安定ではないか」という印象が残りました。こうした懸念が広がると、今後の研修医採用で海外出身者が不利になる可能性があります。
しかし、アメリカ医療にとってIMGの存在は欠かせません。そもそも米国内の医学部卒業生だけでは、毎年用意される研修医ポストを埋めることができません。約6,000人の外国人医師が毎年米国の研修プログラムに参加しており、多くが内科、家庭医、精神科などのプライマリケア(初期診療)分野に従事しています。
特に、医師不足が深刻な地方や農村部では、外国人医師が地域医療を支えています。米国人口の約20%が農村部に住んでいるにもかかわらず、そこで開業する医師は全体の10%ほど。その中でもIMGが大きな割合を占め、彼らの多くは「コンラッド30制度」という仕組みを利用して働いています。これは、医師が一定期間、医療過疎地域で勤務することを条件にビザの制約を免除する制度で、1994年以降、2万人以上の医師がこの制度を通じて地域医療に貢献してきました。
つまり、J-1ビザ問題で研修が遅れれば、地方医療の現場で診療を担う人材がいなくなる──その影響は直接、患者さんの受診機会の減少につながります。
さらに、国内の医学部でも学費高騰や学生ローン制限が進み、経済的に恵まれない層の進学が難しくなっています。結果として、将来の医師供給が細り、外国出身医師の役割はいっそう大きくなると予想されています。
筆者のソレンコワ医師は、今こそ「米国で働く外国人医師の制度的な安定化」が必要だと訴えます。たとえば、J-1ビザの面接予約を優先的に扱う仕組みや、行政上の混乱が起きた場合の緊急対応策を整えること。病院側にとっても、「マッチした研修医が確実に7月から勤務できる」という信頼が必要です。
地方の医療を支えるのは、名門大学出身の専門医だけではありません。異なる文化圏から来た多様な医師たちが、地域の患者に寄り添いながら診療を続けているのです。今回のビザ混乱は、国際的な医療連携の重要性を改めて私たちに教えてくれました。
(出典:Solenkova N. International Medical Graduates, Visa Disruptions, and the Future of the US Physician Workforce. JAMA. 2025;334(17):1513-1514.)




コメント