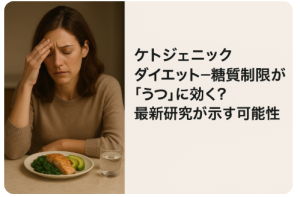 タイトル:ケトジェニックダイエット──糖質制限が「うつ」に効く?最新研究が示す可能性
タイトル:ケトジェニックダイエット──糖質制限が「うつ」に効く?最新研究が示す可能性
2025年11月に JAMA Psychiatry に発表された大規模解析が注目を集めています。
テーマは「ケトジェニックダイエット(以下KD)」と「うつ・不安」の関係です。食事法が精神の健康にまで影響を与えるという報告は、医療の現場でも関心を呼んでいます。今回は、その研究の背景と結果を、一般の方にも分かりやすくまとめます。
◎ケトジェニックダイエットとは
KDは、炭水化物を極端に減らし、脂肪を主なエネルギー源とする食事法です。
通常、私たちの脳はブドウ糖をエネルギーにしていますが、糖質を制限すると体は脂肪を分解し、「ケトン体」という物質を作り出します。これが脳の代替エネルギーとなる状態を「ケトーシス」と呼びます。
この方法は1920年代に難治性てんかんの治療として開発されました。ケトン体が神経の興奮を抑え、発作を減らす効果があるためです。その後、減量法としても知られるようになりましたが、最近では「脳の代謝を整える」効果に再注目が集まっています。
脳内では、エネルギー不足や酸化ストレス、慢性炎症がうつ病や認知症の発症と関係していることがわかっています。KDは、これらに関わるミトコンドリアの働きを高め、炎症を抑え、神経伝達を安定化させると考えられています。
◎研究の目的と方法
今回の研究は、カナダとオーストラリアの研究チームが行ったシステマティックレビューとメタアナリシスです。
これは、過去の複数の研究を統合して統計的に再解析し、全体的な傾向を見極める手法です。
対象となったのは、成人4万人以上・50本の論文。うち10件はランダム化比較試験(RCT)、9件は準実験研究で、KDを実践した人のうつや不安の変化を、心理スケールで測定した結果を比較しました。
◎主な結果
結果として、
-
うつ症状については「小~中程度の改善」が見られました。特にケトン体をきちんと測定し、糖質制限が厳格だった研究ほど改善効果が大きい傾向にありました。
-
一方、不安症状に関しては明確な効果は確認されませんでした。
-
準実験研究では、うつ・不安ともに改善を示す報告が多くありましたが、研究デザインのばらつきが大きく、確実な結論には至っていません。
研究者は、「KDはうつ症状を軽減する可能性があるが、まだ証拠は限定的。より長期で厳密な臨床試験が必要」としています。
◎なぜ食事が心に影響するのか?
KDによる心理的改善の理由は、いくつかの生物学的メカニズムで説明されます。
-
ミトコンドリアの活性化
ケトン体はブドウ糖より効率よくエネルギーを作り、細胞の“発電所”であるミトコンドリアを強化します。これは脳のエネルギー不足を補う可能性があります。 -
炎症と酸化ストレスの抑制
慢性的な炎症や酸化ストレスは、うつ病や認知症のリスクを高めます。KDは抗炎症性サイトカインのバランスを改善します。 -
神経伝達物質の安定化
GABA(抑制性)とグルタミン酸(興奮性)のバランスが整うことで、神経活動の安定が促され、気分が落ち着くと考えられています。
◎注意点と今後の課題
KDはもともと医療管理下で行われる療法です。炭水化物を極端に制限すると、低血糖、倦怠感、便秘、脂質異常などの副作用が起こることもあります。
特に糖尿病や心疾患のある方は、医師の指導なしに自己流で始めるのは危険です。
また、研究の多くは短期間のものであり、「どの程度続ければよいのか」「どんな人に合うのか」についてはまだ定まっていません。
◎まとめ
今回のJAMA Psychiatryの報告は、「食事が心に影響を与える」という新しい視点を後押しするものでした。
ケトジェニックダイエットは単なるダイエット法ではなく、脳の代謝と神経機能を改善する可能性を持つ栄養療法として研究が進んでいます。
今後は、栄養・代謝・精神の三つを結ぶ「栄養精神医学(Nutritional Psychiatry)」がさらに注目されるでしょう。
うつや不安で悩む人にとって、「食事でできる支え」が科学的に確立される日が近づいているのかもしれません。




コメント