 救急外来で「目の奥」をすぐに見る時代へ
救急外来で「目の奥」をすぐに見る時代へ
―― 散瞳しなくてもできるOCTが、診断を大きく変えています ――
突然、視力が落ちた、見え方が変だ、片目が赤い、物が二重に見える――。こうした症状で救急外来を受診される方は少なくありません。しかし実際には、救急外来に常に眼科医が待機していることはまれで、その結果、「念のため専門病院へ転送」「とりあえず様子見」といった対応が多くなりがちでした。
以前は、目の奥を詳しく調べるためには散瞳(瞳を広げる点眼)を行う必要があり、時間もかかり、救急の現場では簡単に行えない検査でした。しかし近年、無散瞳でも撮影できる眼底写真とOCT(光干渉断層計)が普及し、状況は大きく変わりつつあります。
今回紹介する研究は、一般の救急外来において、非散瞳眼底写真とOCT(NMFP-OCT)を用いることで、視覚症状の原因をどこまで迅速に判断できるかを検証したものです。研究は16日間という短期間に行われましたが、その間に救急外来を受診した約1800人のうち、約10%が「見え方の異常」を訴えていました。その多くに、散瞳を行わずにOCT検査が実施されています。
結果として、OCTを受けた患者さんの約6割で、診断に役立つ異常所見が見つかりました。特に有用だったのは、網膜や視神経など、目の奥(後眼部)の病気や、神経に関係する病態でした。視神経乳頭浮腫の有無、網膜剥離や硝子体出血、網膜や黄斑の病変、さらには「異常がないことを確認する」目的でも、OCTは大きな力を発揮しました。
重要なのは、この検査によって「今すぐ眼科医が必要なケース」と「緊急性が低いケース」を、その場でふるい分けられる点です。これにより、不要な転院を減らし、本当に急ぐべき患者さんを早く専門治療につなげることが可能になります。さらに、撮影された画像をもとに遠隔で眼科医が判断する体制(遠隔眼科)への道も開かれます。
救急外来での眼科診療は、これまで「人手が足りない」「判断が難しい」分野でした。しかし、非散瞳OCTという技術の進歩により、「まず画像で見て判断する」時代が現実のものになりつつあります。これは患者さんにとっても、医療現場にとっても、大きな前進と言えるでしょう。
出典
McHenry JG, Lin MY, Pendley AM, et al.
Nonmydriatic Fundus Photography–Optical Coherence Tomography Imaging for Visual Symptoms in the Emergency Department
Ophthalmology:第133巻 第2号 p178–186(2026年2月)
眼科医・清澤のコメント
以前は、救急外来で眼の奥を評価するには「まず散瞳」が前提でした。しかし現在は、非散瞳OCTが使えることで、その場で視神経や網膜の状態を客観的に把握できる時代になっています。これは単なる検査の進歩ではなく、「迅速に正しい判断をする医療」への大きな転換点だと感じています。救急医と眼科医をつなぐ共通言語として、OCT画像の価値は今後さらに高まっていくでしょう。
結果部分の直訳をここにつけておきます;


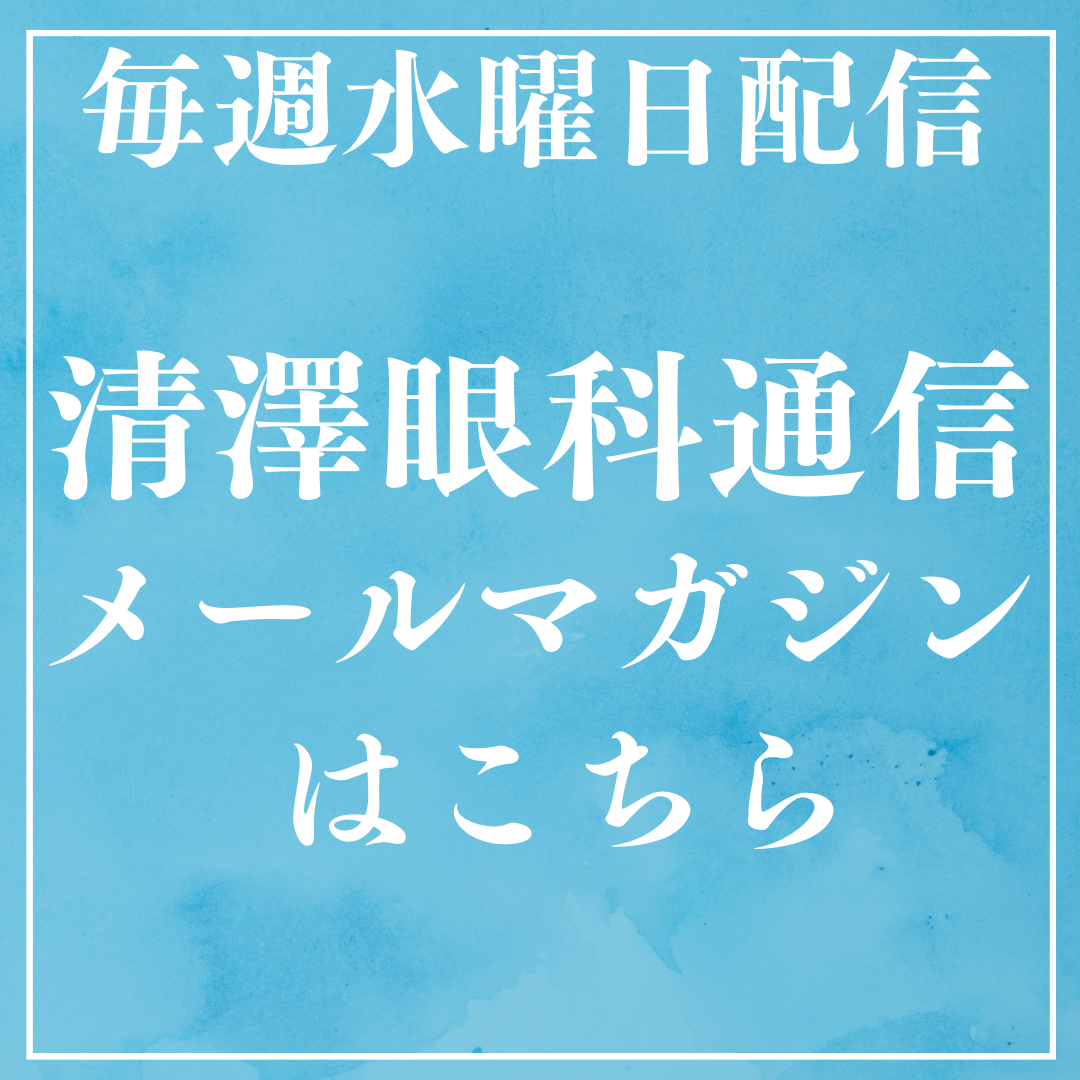

コメント