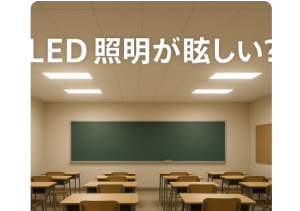 学校教室のLED照明──「明るすぎ」「調節できない」は本当?
学校教室のLED照明──「明るすぎ」「調節できない」は本当?
眼科の立場から考える、子どもの目と照明環境
近年、全国の学校で照明が蛍光灯からLEDに置き換えられています。省エネや長寿命が利点ですが、一部では「LED照明は明るすぎる」「調光できない」といった声も聞かれます。眼科医の立場から、照明環境が子どもの目に与える影響を整理してみましょう。
① LED照明は本当に「明るさを調節できない」のか?
「LEDだから調光できない」というのは誤解です。LED自体はむしろ調光しやすい光源で、0–10V制御やDALI制御といった方式を用いれば、明るさを滑らかに変えられます。ただし、学校で実際に導入されている照明器具が“非調光タイプ”である場合、明るさは固定になります。
多くの学校では予算や工期の都合で調光機能を省略しているのが現状です。したがって、「LEDなのに調節できない」のではなく、「調光機能を備えていない照明システムが多い」と理解するのが正確です。
② 教室照明に求められる明るさと均一性
文部科学省の「学校環境衛生基準」では、教室の机上照度を300ルクス以上(望ましくは500ルクス程度)としています。黒板面も同様で、照度のばらつき(明るさのムラ)は最大/最小が20:1を超えないことが求められます。
欧州の基準(EN12464-1)ではさらに「均一性U₀≥0.6」「UGR(不快グレア)≤19」が推奨されています。UGRとは「まぶしさの感じにくさ」を表す国際指標で、19以下が“快適な教室環境”の目安です。つまり、明るさの数値だけでなく「均一でまぶしくない」ことが重要なのです。
③ 明るすぎる照明は本当に問題ないのか?
人の目は明るい環境では瞳孔が縮み、網膜の感度(明順応)が下がります。これにより光の刺激がある程度抑えられるため、「多少明るくても大丈夫」という考えには一理あります。
しかし、次のような注意点があります。
-
縮瞳には限界がある:強い光や眩しさが続くと、眼精疲労や注意力低下を招く。
-
まぶしさ=グレアの問題:白板やタブレットの反射が強いと、板書が見えにくくなる。
-
明るさのムラによる疲労:窓際と後方の照度差が大きいと、目の順応を繰り返すため疲れやすい。
-
長時間の累積負荷:毎日の授業で高照度環境が続くと、近見作業時のピント調節負担が増し、眼精疲労や学習能率の低下につながる。
したがって「明るすぎても問題ない」とは言い切れません。均一で快適な光環境こそが理想です。
④ LED照明特有の注意点
LEDには**フリッカー(ちらつき)**と呼ばれる時間的光変動があり、低周波や変調の深い光は頭痛や眼の疲れの原因になることがあります。
また、白色LEDには青色光成分が多く含まれますが、一般照明用製品は国際安全基準上「低リスク(RG1以下)」に分類されており、通常の教室使用で網膜障害を起こす危険はありません。むしろ昼間の青白い光は体内時計を整える効果もあり、日中の活動にはプラスに働きます。
⑤ 望ましい教室照明とは?
快適な教室照明をつくるためには、次の要素がそろっていることが理想です。
-
机上照度300~500ルクス、黒板も均一に照らす
-
照度のムラを少なく(U₀≥0.6)
-
まぶしさ指標UGR≤19を守る
-
ちらつきの少ない調光システムを採用
-
昼光を上手に取り入れ、窓際は自動減光
これらを設計段階から考慮すれば、「明るすぎる」「まぶしい」といった問題は大きく減らせます。
⑥ まとめ:子どもの目を守るために
LED照明は正しく設計・運用すれば、蛍光灯よりも省エネで安定した光を提供できます。ただし、調光機能がない、照度が過剰、グレア対策が不十分な教室では、児童の集中力や視覚快適性に悪影響を及ぼす可能性があります。
「明るければ良い」ではなく、「快適に見える明るさ」を目指すことが大切です。ご家庭でも、お子さんの勉強机の照明がまぶしすぎないか、一度確認してみてください。
参考文献
文部科学省「学校環境衛生基準」/EN12464-1/IEEE1789-2015/CIE Position Statement on Blue Light Hazard




コメント