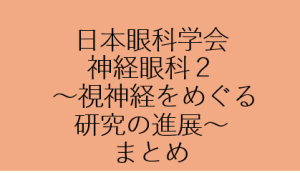
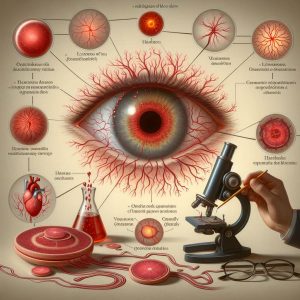 神経眼科の最前線報告 ~視神経をめぐる研究の進展~日本眼科学会より:
神経眼科の最前線報告 ~視神経をめぐる研究の進展~日本眼科学会より:
清澤のコメント:2025年4月に開催される日本眼科学会では、神経眼科の分野でも最新の研究が数多く提出されています。本記事では、「神経眼科2:遺伝・循環」のセッションから注目の6演題をご紹介します。視神経の病変や血流変化、遺伝性の視神経症に関する研究が主に取り上げられ、視機能との関連や治療法のヒントが見えてきました。画像診断の進歩とiPS細胞などの再生医療技術の発展により、これまで見えなかった視神経の病態が少しずつ明らかになってきています。特に、レーベル病に関する一連の研究は、今後の治療法の確立にも大きく寄与することが期待されます
1. 視神経が曲がることで起きる視力低下のメカニズム(群馬大学・篠原洋一郎先生)
トルコ傍鞍部腫瘍(下垂体腫瘍など)は、視神経を押し曲げることで視力を著しく低下させることがあります。この研究では、視神経が45度以上屈曲している16例を対象に、手術前後の視力・視野・網膜の血流を詳しく分析。術後、血流の改善が確認され、術前の網膜細胞の状態が術後回復の目安になる可能性が示されました。
2. NAIONと正常眼圧緑内障の視神経血流の違い(宮崎大学・田村弘一郎先生)
「非動脈炎性虚血性視神経症(NAION)と正常眼圧緑内障(NTG)」は、どちらも視神経の障害で見えにくくなる病気です。本研究では、視野が横方向に欠ける患者で、視神経の血流を測定。NAIONでは血流の低下と視野障害が一致しないことが多く、NTGでは視野の悪化に比例して血流が落ちるという違いが明らかになりました。
3. OCTAでみるレーベル遺伝性視神経症の急性期変化(京都大学・伊藤宗桂先生)
「レーベル遺伝性視神経症(LHON)」は若年男性に多い急激な視力低下を伴う遺伝性疾患です。この研究では、発症1ヶ月以内の患者でOCTA(網膜の血管を可視化する画像技術)を使って、視神経周囲の血管密度を解析。上側の血流が増加し、耳側が低下するという独特なパターンが見られ、病態の一端が明らかになってきました。
4. 一酸化窒素とレーベル病の関係を探るオルガノイド研究(神戸大学・高野史生先生)
iPS細胞技術で作製した網膜オルガノイド(試験管内の擬似網膜組織)を用いて、LHON患者の病態を再現。一酸化窒素が網膜細胞死を増やす可能性があり、患者由来の細胞では防御反応(ミトコンドリアDNAの増加)がうまく働かないことがわかりました。今後の新しい治療の開発に役立ちそうです。
5. レーベル病の実態を明らかにする全国疫学調査(神戸大学・上田香織先生)
これまであまり実態がわかっていなかったLHONの全国調査が進んでいます。2024年までに323名の患者データを集積し、発症年齢の中央値は33歳、96%が既知の三大遺伝子変異を持っていることが判明しました。高齢発症や特定の遺伝子型が視力の悪化と関係しており、今後の診断や予後予測に役立つ情報となりそうです。
。




コメント