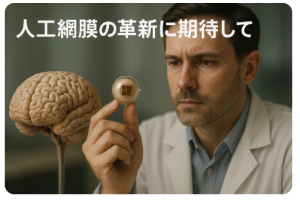 脳科学的アプローチからの人工網膜の革新に期待して
脳科学的アプローチからの人工網膜の革新に期待して
――第63回日本神経眼科学会・森本壮会長のシンポジウムでの講演を前に――
人工視覚の研究は、長らく「脳に電極を置く方式」と「網膜に電極を置く方式」という二つのアプローチで進められてきました。脳表面に電極を直接配置し、失明患者の視覚野を刺激する試みは、ユタ大学をはじめとする海外の研究で一定の光覚(フォスフェン)の誘発に成功した報告がありました。私が大学に在籍していた頃にもそのプロジェクトに関心を持ち、ユタ大学との間で書簡のやり取りをした記憶があります。グラントを獲得し、脳外科チームを組んで患者負担のない形で手術を実施できる体制を整えれば、初期型の装置を提供できるとの返答を受けたものの、当時はそこから先に進むことはできませんでした。
一方、網膜側に電極を設置する「人工網膜(網膜刺激型)」の研究は、その後大きく進展しました。特に大阪大学の森本壮先生は、脈絡膜上・経網膜刺激(STS)法という独自の方式で臨床応用を進め、世界的にも注目されています。今回、第63回日本神経眼科学会の会長として、森本先生が「脳科学的アプローチからの人工網膜の革新とその先にある未来」というテーマで講演をされることは、この分野の次のステージを示す象徴的な出来事といえるでしょう。
講演では、おそらく以下のようなキーワードが軸となると思われます。すなわち、人工網膜(網膜刺激型)、残存神経と神経回路の可塑性、脳科学的アプローチ(網膜から視神経、視覚野への情報伝達)、刺激方式・電極配置・空間分解能、画像処理・AIによる最適化、そして次世代の革新:再生医療との併用・高機能化・社会実装。また、患者さんの視点―何が見えるのか、何が見えないのか、どこまで期待できるのか―、そして最後には、未来の姿として「視覚補助から視覚拡張へ」という展望も語られるのではないでしょうか。
人工網膜の研究は、単なる医療機器の開発を超え、「脳と心がどのように世界を“見る”のか」を探る壮大な挑戦でもあります。森本先生の講演が、この領域の科学的深化と臨床応用の橋渡しとなることを期待しています。




コメント