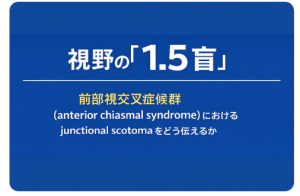 視野の「1.5盲」――前部視交叉症候群(anterior chiasmal syndrome)における junctional scotoma をどう伝えるか
視野の「1.5盲」――前部視交叉症候群(anterior chiasmal syndrome)における junctional scotoma をどう伝えるか
視野障害の診断では、「どの部分が、どのように欠けているか」が病変部位を推定する重要な手がかりになります。
なかでも、視神経と視神経交叉の“境目”に病変が及んだときにみられる特徴的な視野障害は、学生や研修医にとっても理解が難しく、患者さんへの説明にも工夫が必要な領域です。
この部位の障害でみられる典型的な視野所見は、
**片眼の高度視力低下(ときに失明レベル)**と、
反対眼の耳側半盲(しばしば上耳側)
が同時に存在するというものです。
私はこの状態を、患者さんやレジデントに説明する際、やや独断的ではありますが
「視野の1.5盲」
と表現しています。
一方の眼は、視神経そのものが障害され「1盲」に近い状態にあり、
もう一方の眼は、視野の半分、すなわち「0.5盲(半盲)」が生じている。
両者を合わせると、確かに“1.5”という感覚が直感的に理解しやすいのです。
この「1.5盲」に相当する病態は、医学的には
junctional scotoma(接合部暗点)
あるいは
anterior chiasmal syndrome(前部視交叉症候群)
として知られています。
病変の本態は、視神経が視神経交叉へ移行する直前の領域にあります。
この部位は、解剖学的にも機能的にも非常に重要で、鞍上部に発生する腫瘍――たとえば下垂体腺腫、頭蓋咽頭腫、髄膜腫、あるいは動脈瘤など――による圧迫を受けやすい場所です。
病変がこの領域に及ぶと、
・同側では視神経が直接障害され、中心暗点や急激な視力低下を生じ、
・反対側では、視神経交叉に入る鼻側網膜由来の線維が侵され、耳側半盲が出現します。
かつてはこの視野パターンを「Wilbrand膝」という特殊な神経線維走行で説明する考え方が広く知られていましたが、近年ではその解剖学的実在性には否定的な見解が主流です。現在は、比較的大きな病変が視神経と視交叉を同時に圧迫する結果として理解する方が妥当とされています。
重要なのは、視野検査でこの「1.5盲」に相当する形を見逃さないことです。
片眼の視力低下だけに目を奪われてしまうと、反対眼の耳側半盲という“警告サイン”を見過ごす危険があります。
この視野パターンを認識した時点で、視神経交叉周辺を含めた頭蓋内精査が必須となります。
「視野の1.5盲」という表現は正式な医学用語ではありません。
しかし、**junctional scotoma というやや難解な概念を、臨床の現場で共有するための“橋渡しの言葉”**としては、十分に意味を持つと私は考えています。
専門用語と直感的理解、その両方をつなぐ表現として、今後も使い続けていきたい概念です。


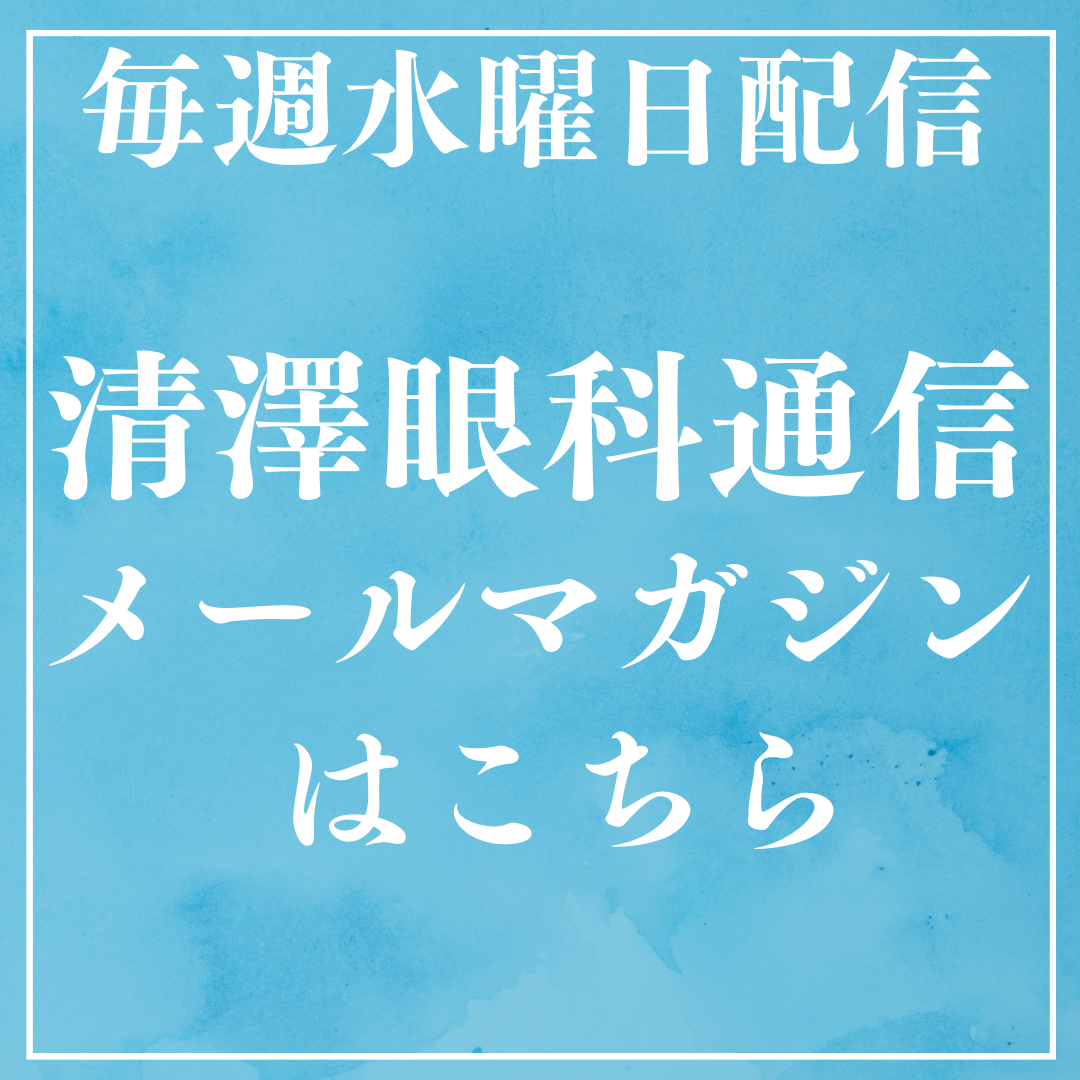

コメント