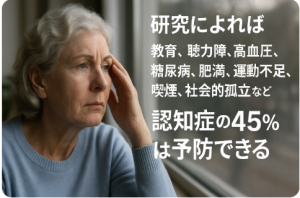 清澤のコメント:高齢者は自らが認知症になることを防ぐための対策をとることが必要ですが、すでに介入が可能ないくつかの要素が知られています。それらに対する介入をすることで、認知症の進行を抑制できるというJAMA誌オンライン版(2025年7月28日公開)に掲載されたJonathan M. Schott医師による論説「Lifestyle Interventions to Improve Cognition in Later Life: When Is Enough Enough?」をもとに、眼科院長ブログ記事を作ってみました。
清澤のコメント:高齢者は自らが認知症になることを防ぐための対策をとることが必要ですが、すでに介入が可能ないくつかの要素が知られています。それらに対する介入をすることで、認知症の進行を抑制できるというJAMA誌オンライン版(2025年7月28日公開)に掲載されたJonathan M. Schott医師による論説「Lifestyle Interventions to Improve Cognition in Later Life: When Is Enough Enough?」をもとに、眼科院長ブログ記事を作ってみました。
高齢期の認知機能を守るには?──生活習慣の見直しで認知症予防を
はじめに:認知症予防は今できることから
高齢期における認知症の予防は、現代社会が直面する重要な課題の一つです。認知症の原因はアルツハイマー病などの神経変性疾患だけでなく、脳血管障害やそれらの混合型も多く存在します。薬物治療だけでなく、生活習慣の改善による予防効果が期待されています。
研究によれば、教育、聴力障害、高血圧、糖尿病、肥満、運動不足、喫煙、社会的孤立など14の要因を修正すれば、認知症の45%は予防できるとされます。
生活習慣改善の新たな大規模試験「US POINTER」
米国で行われた「US POINTER」試験は、健康だが認知症リスクの高い60~79歳の約2,000人を対象に、2年間にわたり生活習慣介入を行った研究です。対象者はいずれも運動不足で、食生活や心血管リスクに課題がありました。
参加者は以下の2群に分けられました:
-
自己管理群:健康や運動、食事に関する情報提供を受け、自ら取り組むスタイル。6回の面談やピアミーティングが含まれました。
-
構造化介入群:専門家チームによる38回のセッション、健康コーチング、食事指導、高強度の運動、認知トレーニングなどを実施する本格的なプログラムです。
認知機能への効果は?──どちらの介入も有効
2年後、どちらの群でも記憶力や注意力、情報処理スピードの改善が見られ、特に構造化介入群ではわずかに大きな改善(平均+0.243SD/年 vs 自己管理群+0.213SD/年)が認められました。
特徴的だったのは、「実行機能(段取りや判断力など)」の改善が大きく、これは脳血管性の要素が影響した可能性を示唆しています。一方で、記憶力は18か月以降に低下傾向を示しており、アルツハイマー型の予防には限定的かもしれません。
限界と現実的な課題
この試験の意義は大きいものの、以下のような制限があります。
-
対照群(何もしない群)が存在しないため、真の効果判定が難しい
-
参加者の動機付けが高く、ITリテラシーも高めであり、一般的な高齢者全体に当てはまるとは限らない
-
介入が認知症の根本的病変にどう影響するかは不明
-
構造化介入は高コストであり、広く実施するには現実的なハードルがある
結論:小さな変化でも続けることが大切
この研究の最大の教訓は、「徹底的な介入をしなくても、比較的簡単な生活改善だけでも効果がある」ということです。たとえば運動を始める、食生活を整える、人と交流するだけでも、認知機能を守る助けになります。
高齢化が進む中、医療現場ではこうした介入を早期から導入し、地域ぐるみで支える仕組み作りが求められるでしょう。
院長コメント
眼科診療の現場でも、高齢者の認知機能低下はしばしば見受けられます。見えにくくなったから外出が減り、閉じこもりがちになると、認知機能の低下に拍車がかかることもあります。目の健康と認知機能は深くつながっていると改めて実感しました。患者さんの生活全体に目を向ける姿勢が、眼科医にも求められているのかもしれません。
出典
Schott JM. Lifestyle Interventions to Improve Cognition in Later Life—When Is Enough Enough? JAMA. Published online July 28, 2025. doi:10.1001/jama.2025.12500
US POINTER trial(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03688126)
FINGER trial(Ngandu et al., Lancet, 2015)




コメント