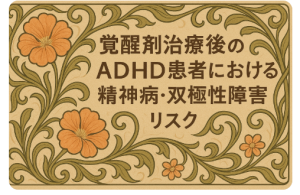 覚醒剤治療後のADHD患者における精神病・双極性障害リスク
覚醒剤治療後のADHD患者における精神病・双極性障害リスク
――システマティックレビューとメタアナリシス(JAMA Psychiatry, 2025)
① 論文の概要
今回ご紹介するのは、「覚醒剤で治療された注意欠陥/多動性障害患者における精神病および双極性障害の発生」という論文です。
著者はゴンサロ・サラザール・デ・パブロ博士らの国際研究チームで、権威ある JAMA Psychiatry に2025年9月3日にオンライン掲載されました(DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2025.2311)。
② 背景
注意欠陥/多動性障害(ADHD)は、子どもから大人にかけて広く見られる神経発達障害で、集中の持続困難、多動、衝動性といった症状を示します。治療の第一選択肢としてしばしば用いられるのが「覚醒剤(メチルフェニデートやアンフェタミン製剤)」です。これらは学習や日常生活の改善に効果的ですが、副作用として稀に精神病や躁状態が報告されてきました。ただし、それがどの程度の頻度で起こるのか、薬剤間で差があるのかは、これまで明確ではありませんでした。
③ 目的
研究チームは、
-
ADHD患者が覚醒剤治療を受けた後に 精神病 または 双極性障害(BD) を新たに発症する頻度を明らかにすること
-
どのような条件でリスクが高まるかを検討すること
を目的に、システマティックレビューとメタアナリシスを行いました。
④ 方法
-
データ収集:PubMed、Web of Science、PsycINFO、Cochraneなど主要データベースを網羅的に検索(2024年10月1日まで)。
-
対象:DSMまたはICDに基づき診断されたADHD患者で、覚醒剤治療歴があり、その後の精神病やBDの発症が追跡された研究。
-
解析:PRISMAガイドラインに従い、16件の研究(合計391,043人)を抽出。ランダム効果モデルで統合解析し、薬剤ごとの比較やサブグループ分析も実施。
⑤ 結果
-
発症率
-
精神病症状:2.76%
-
精神病性障害:2.29%
-
双極性障害:3.72%
→ 少数ではあるが「無視できない頻度」で発生していることが判明しました。
-
-
薬剤間の比較
-
アンフェタミン製剤を使用した群の方が、メチルフェニデート群より精神病のリスクが有意に高い(OR 1.57)。
-
-
リスクを高める要因
-
女性の割合が高い群
-
観察期間が長い研究
-
高用量の使用
-
サンプルサイズが小さい研究
-
⑥ 結論
この研究は、覚醒剤治療を受けたADHD患者において、精神病や双極性障害の新規発症が一定の割合で見られることを明らかにしました。特にアンフェタミン系薬剤ではリスクが高く、臨床現場では投与開始時から注意深いモニタリングが必要です。
また、今回の解析は観察研究に基づいており因果関係を証明するものではありません。今後、ランダム化比較試験などによる更なる検証が望まれます。
⑦ 臨床への示唆
-
覚醒剤はADHD治療に有効である一方、副作用として稀に重大な精神疾患を誘発する可能性がある。
-
投与前には患者と家族にリスクを説明し、心理教育を行うことが重要。
-
治療中も定期的な問診や行動観察を通じて精神状態をモニタリングし、異変があれば早期対応することが推奨されます。
清澤のコメント
眼科臨床とは直接関係しませんが、ADHDは小児・若年層で多く、私たちの患者さんの中にも併存する例があります。覚醒剤治療によって学業や生活が改善する一方で、まれに精神病や双極性障害を引き起こす可能性があるという報告は、医療者だけでなくご家族にとっても知っておくべき重要な情報です。眼科の診察でも、学校生活や精神面での変化に気づいた際には、小児科や精神科との連携が求められるでしょう。
📖 出典:
Salazar de Pablo G, Aymerich C, Chacartegui Pascual JP, et al. Incidence of Psychosis and Bipolar Disorder in Patients With ADHD Treated With Stimulants: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online September 3, 2025. doi:10.1001/jamapsychiatry.2025.2311




コメント