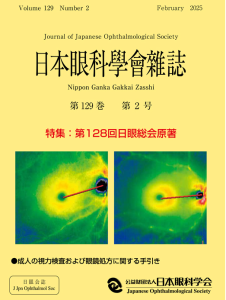 成人の視力検査および眼鏡処方に関する手引き(成人視力検査眼鏡処方手引き作成委員会、委員長大鹿哲郎氏)が日本眼科学会誌2月号に収載され、その全文がネットでも閲覧できます。本日は、このブログで紹介する第一回目として、臨床編の1,成人の資力検査、眼鏡処方のコンセプトと2,視力測定法、の部分を5分の1に抄出してみました。臨床編だけでも以後3-6項まであります。臨床編の全体はP150-197まででA4版の27ページの長大な内容で、その先に基礎編も続いています。膨大なものですが、視力測定の視標や部屋の照明なども詳しく採録されており、一度は目を通しておきたい内容です。
成人の視力検査および眼鏡処方に関する手引き(成人視力検査眼鏡処方手引き作成委員会、委員長大鹿哲郎氏)が日本眼科学会誌2月号に収載され、その全文がネットでも閲覧できます。本日は、このブログで紹介する第一回目として、臨床編の1,成人の資力検査、眼鏡処方のコンセプトと2,視力測定法、の部分を5分の1に抄出してみました。臨床編だけでも以後3-6項まであります。臨床編の全体はP150-197まででA4版の27ページの長大な内容で、その先に基礎編も続いています。膨大なものですが、視力測定の視標や部屋の照明なども詳しく採録されており、一度は目を通しておきたい内容です。
緒言 情報化社会の進展により視覚的ストレスが増大し、屈折矯正の重要性が高まっている。眼科診療における基本的な検査は屈折と視力の測定であり、眼鏡による矯正が最も一般的な手段である。視力検査は眼疾患の発見やスクリーニングにも役立ち、正確な測定が診断や治療に結びつく。眼鏡矯正は安全性や利便性に優れ、屈折矯正の主流である。成人の視力矯正は情報化社会において重要性を増し、老視を含む視機能の適切な管理が求められる。本手引きが臨床現場で活用されることを願い、緒言とする。
I. 臨床編
1. 成人の視力検査・眼鏡処方のコンセプト
-
眼鏡の使用率 眼鏡は最も利用者が多い屈折矯正手段である。成人の眼鏡使用率は74.2%であり、中学・高校時代や老視の始まる40~50代にかけて使用開始することが多い。
-
適切な眼鏡とは 視力測定では最良視力を求めるが、眼鏡処方は日常生活での快適性を重視する。完全矯正眼鏡は調節を強いられ眼精疲労の原因となるため、屈折度のみならず使用環境も考慮した処方が必要である。
-
使用状況に応じた処方 用途に応じた度数設定が求められる。車の運転、PC作業、スマートフォン利用など、異なる距離に対応した眼鏡の使い分けが重要である。また、視機能に制限のある患者に対する処方も慎重に行う必要がある。
2. 視力の測定法
-
視力測定法の概要 視力検査は歴史的に精度向上が議論されてきた。視標の標準規格としてLandolt環が用いられ、日本国内ではJIS T 7309:2002が視力測定の基準となっている。
-
視標の種類や室内照度 視標にはLandolt環、文字視標、図形視標があり、Landolt環が標準とされる。視標の輝度やコントラストの基準も設定されており、視力測定の精度を向上させるために適切な環境が求められる。
-
視力測定の国際基準と日本の規格の違い JIS規格と日本眼科学会の基準には細かな違いがあり、視標のサイズや輝度の許容範囲、視力値の段階などに差異がある。標準的な検査方法の統一と精度の向上が求められる。
視力検査は眼鏡処方の基礎となり、測定の正確性が重要である。適切な屈折矯正を提供し、快適な視生活を支えることが眼科医の役割である。




コメント