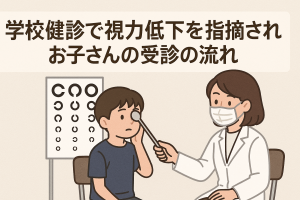
学校健診で視力低下を指摘されたお子さんの受診の流れ
お子さんが学校の視力検査(学校健診)で裸眼視力の低下を指摘された場合、正確な視力の状態や近視の程度を把握するために、以下のようなステップで診察・検査・治療のご提案を行っています。
① 初回検査:ミドリンP点眼による屈折検査(2段階評価)
まず最初に行うのは、「調節緊張(ピントを合わせる筋肉が過剰に働く状態)」の有無を確認するための検査です。これは、ミドリンPという目薬(調節をゆるめる薬)を点眼し、その後に再度屈折検査を行うことで、本来の近視の度合いを調べるものです。
この方法により、「仮性近視(調節緊張による一時的な近視)」と「真の近視(軸性近視など)」を見分けることができます。
なお、ミドリンPや類似の点眼薬には、一時的に調節を解除する効果はありますが、近視の進行を抑える効果はありません。あくまでも検査目的の使用です。
この検査結果をもとに、後日あらためて正確な眼鏡処方を行います。
② 次の選択肢:低濃度アトロピン点眼による近視進行抑制(自由診療)
眼鏡処方の後、将来的な近視の進行をできるだけゆるやかにするために、低濃度アトロピン点眼(0.01~0.05%)を用いた治療をご提案することがあります。
この点眼薬は、1日1回就寝前に使用することで、近視の進行を平均30~50%程度抑えるという報告が多くの研究で示されています。
ただし、この治療は自由診療(自費診療)となります。費用・期間・効果などについては、医師が個別にご説明し、ご相談のうえで開始するかを決定します。
③ さらに進んだ治療法:オルソケラトロジー(特殊ハードコンタクトレンズ)
さらにご理解・ご希望があれば、近視進行抑制効果がある「オルソケラトロジー」という治療法もご案内可能です。
これは、夜間のみ装用する特殊なハードコンタクトレンズで、角膜の形を調整することにより、日中は裸眼で過ごせるようになるとともに、近視の進行を抑える効果も期待されます。
こちらも自費診療となり、装用に向くかどうかは事前に適応検査を行って判断します。ご希望の方には詳しくご説明いたします。
ご家族と相談しながら治療方針を決定します
このように、視力低下を指摘されたお子さんへの対応には、段階的な選択肢があります。
-
調節緊張を評価した上での正確な眼鏡処方
-
低濃度アトロピンによる近視進行の予防
-
さらに高度な進行抑制としてのオルソケラトロジー
どこまでの治療を行うかは、お子さんの生活スタイルやご家族のご意向を踏まえて、医師と相談しながら決めていきます。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。




コメント