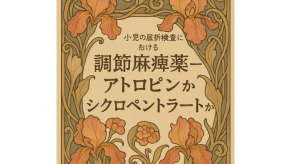 小児の屈折検査における調節麻痺薬 ― アトロピンかシクロペントラートか?
小児の屈折検査における調節麻痺薬 ― アトロピンかシクロペントラートか?
小児の屈折検査を正確に行うためには、調節力をしっかり麻痺させることが不可欠です。毛様体筋が働いたままでは遠視や近視の度数が正確に測れず、特に遠視は過小評価されてしまいます。日常診療で「アトロピンを使うべきか、シクロペントラートで十分か、それともトロピカミドで済むのか」という判断に悩むことは少なくありません。
2025年9月25日号の JAMA Ophthalmology に、このテーマに関して中国・上海の大規模研究を取り上げた論説が掲載されました。著者はアラバマ大学バーミンガム校の Katherine K. Weise 先生らで、Wuらの研究を批判的に評価しています。以下に要点を整理します。
■ 背景:調節麻痺薬の特性
-
シクロペントラート(1%)
25〜75分で効果発現、6〜24時間持続。標準的に使われる。 -
トロピカミド
4〜8時間とさらに短いが、一定の効果を示す場合もある。 -
アトロピン(1%)
効果発現は遅く(60〜180分)、最大で7〜12日間持続。強力である反面、羞明や近見障害など副作用の負担が大きい。
■ Wuらの研究(上海での比較)
Wuらは3〜7歳児を対象に、約10年の間隔をあけた二つの大規模集団研究を比較しました。
-
アトロピン群(2024年):1%アトロピンゲルを4日間連続点眼。
-
シクロペントラート群(2013〜2014年):通常の2回点眼プロトコル。
その結果、
-
前近視(プレマイオピア)の有病率
アトロピン群:8.7%
シクロペントラート群:21.6%
→ シクロペントラートは前近視を過大評価している可能性。 -
平均屈折度数の差
アトロピン群の方がわずかに遠視寄り(差は約0.6D)。
著者らは「アトロピンにより前近視を過大診断するリスクを避けられる」と結論しました。
■ Weiseらの論説の指摘
Weise先生らはこの結果を評価しつつも、以下の問題点を指摘しています。
-
研究デザインの限界
二つの集団が10年も隔たっており、生活習慣や近視予防活動の影響を排除できない。 -
副作用データの欠如
羞明や近見困難といったアトロピンの副作用に関する情報が報告されていない。数日〜1週間にわたる視機能低下を小児が受け入れられるかは疑問。 -
臨床適用の現実性
「小児に毎日1%アトロピンを数日間点眼する」というプロトコルは、診療の現場では非現実的。
結論として、「アトロピンの方がより正確に測定できる可能性はあるが、日常臨床で標準にすべきとまでは言えない」と述べています。
■ 臨床への示唆
小児の屈折検査では、診断の精度と患者負担(羞明や近見障害)を天秤にかける必要があります。シクロペントラートは比較的短時間で効果が切れ、日常生活への影響も少ないため現実的です。アトロピンは、強い遠視や偽近視を詳細に評価する必要がある症例など、限られた場面で選択肢となるでしょう。
■ 清澤のコメント
小児の屈折検査においては「強い薬が必ずしも正しい結果をもたらすわけではない」という点が重要です。確かにアトロピンは強力ですが、数日間続く副作用を考慮すると標準的な方法とはなりにくいでしょう。臨床の現場では、依然としてシクロペントラートが第一選択であり、症例に応じてアトロピンを補助的に使うという判断が現実的だと思います。
出典
-
Katherine K. Weise, OD, MBA; Safal Khanal, OD, PhD.
Commentary on Cycloplegic Refraction in Children: Atropine vs Cyclopentolate.
JAMA Ophthalmology. Published online September 25, 2025.
doi: 10.1001/jamaophthalmol.2025.3342




コメント