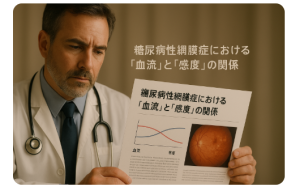 糖尿病性網膜症における「血流」と「感度」の関係を追う
糖尿病性網膜症における「血流」と「感度」の関係を追う
― JAMA Ophthalmology(2025年10月30日)掲載論文より ―
2025年10月30日にオンライン公開された JAMA Ophthalmology の論文「糖尿病性網膜症における網膜感受性と網膜灌流(Retinal Sensitivity and Perfusion in Diabetic Retinopathy)」は、糖尿病による視力障害の背景にある網膜の血流変化と感度の関係を詳しく調べた研究です。
糖尿病性網膜症(DR)は、血糖コントロールが不良な状態が続くことで網膜の細い血管が障害を受け、酸素や栄養の供給が不足し、視機能が低下していく病気です。従来、毛細血管が詰まる「非灌流」領域が広がるほど視力に悪影響を与えると考えられてきましたが、実際にどの程度血流の減少と視機能の低下が対応しているのか、またその関係が時間とともにどう変化していくのかは、十分に明らかになっていませんでした。
この研究は、イギリスの大学病院で行われた前向き縦断研究で、2018年から2024年にかけて中等度から重度の非増殖性、あるいは高リスク未満の増殖性糖尿病網膜症を持つ成人患者44名を対象にしています。いずれの患者もまだレーザー治療や抗VEGF薬の投与を受けていない段階で、他の網膜疾患もないことが条件でした。研究チームは、患者の片眼または両眼を最長2年間追跡し、網膜の血流と機能の変化を比較しました。血流の評価には超広角蛍光眼底造影(UWF-FA)が用いられ、網膜感度は広範囲(110度)のマイクロペリメトリーで測定されました。
対象者の平均年齢は52歳で、約3割が女性でした。血糖コントロールは全体的に不良で、平均ヘモグロビンA1cは9.1%に達していました。初診時の結果では、血流が保たれている「灌流領域」でも感度の低下が見られ、平均で6.6デシベル(dB)の感度欠損が認められました。一方で、血流が失われた「非灌流領域」では平均11.8dBの感度低下があり、灌流領域よりも明らかに大きな機能障害が生じていました。しかし興味深いことに、非灌流領域のうち約30%は正常な感度を維持しており、血流が途絶しても網膜が一定の機能を保つ場合があることが分かりました。
1年後の追跡では、血流のある領域とない領域の双方で感度が徐々に低下しましたが、その差は統計的に有意ではありませんでした。2年目になると、非灌流領域での低下がやや顕著になり、血流状態による違いが明確になりました。それでも全体としては感度の低下速度が時間の経過とともに緩やかになり、初年度に比べて約45%程度の低下率の減少がみられました。
この結果は、網膜の血流状態が視機能に密接に関係することを裏付ける一方で、単純に「血流があれば感度が保たれる」「血流がなければ感度が失われる」といった直線的な関係ではないことを示しています。血流が失われてもなお感度を保っている領域が存在するという事実は、網膜が代償的な機能回復や神経可塑性を発揮している可能性を示唆しています。
また、灌流が残る領域でも感度が低下していた点は、糖尿病による網膜神経組織そのものの障害が血管の変化よりも先行している可能性を示しています。このことから、糖尿病網膜症の視機能低下は単なる血管障害の結果ではなく、神経の代謝異常や慢性炎症が関与していることも考えられます。
研究の意義として、著者らはこの知見が今後の臨床試験の設計や新しい治療戦略の立案に役立つと述べています。毛細血管の非灌流を改善する再生医療的アプローチや、感度を維持するための神経保護的治療を検討する上で、血流と機能の両面を長期的に評価することが欠かせないとしています。
この報告は、糖尿病性網膜症の管理を「血流の画像で見る病気」から「血流と感度の両方をみる病気」へと発展させる重要な一歩といえるでしょう。実際の診療でも、OCTや蛍光眼底造影だけでなく、マイクロペリメトリーなどによる機能的評価を取り入れることで、患者の生活に直結する視機能をより正確に把握できる時代が来ているといえます。
出典:Hamilton-Pele JA, Wright DM, Lim A, et al. Retinal Sensitivity and Perfusion in Diabetic Retinopathy. JAMA Ophthalmology, Published online October 30, 2025. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2025.3980




コメント