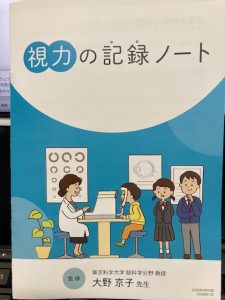 小中学生の近視進行を記録し、家族と共有するために
小中学生の近視進行を記録し、家族と共有するために
―「視力の記録ノート」の活用を始めます―
近年、小中学生の近視が急増しており、その進行をいかに抑えるかが眼科診療における大きな課題となっています。とくにスマートフォンやタブレットの普及により、近距離での作業時間が長くなり、屋外活動が減少している現状では、予防の取り組みがこれまで以上に重要になっています。
そうした中、参天製薬が配布を始めた「視力の記録ノート」は、医師とご家庭が連携し、子どもの目の健康状態を継続的に記録・共有するための強力なツールとなることが期待されています。このノートは、東京科学大学の大野京子教授が監修されたもので、科学的な裏付けのある記録内容が網羅されています。
当院でも今後、近視の診療に来られる小中学生の全員にこのノートを配布し、ご家族と一緒に目の健康を管理していく取り組みを始めます。
ノートの内容と使い方
◆近視の程度を把握する(1ページ)
視力検査で得られるのは裸眼視力や矯正視力だけでなく、「近視の程度(屈折度数)」や「眼軸長」などの重要なデータです。
-
屈折度数(ジオプトリー:D)は近視が進むほどマイナスの値が大きくなります。
-
眼軸長(眼球の前後の長さ)は、長くなることで網膜の手前にピントが合わず、近視が生じます。
これらの数値は、ノート内の表に記入し、ご家庭でも定期的に確認できます(※当院では現在、眼軸長測定器は導入しておりません)。
◆近視進行のグラフ記録(3〜6ページ)
男子・女子それぞれの進行曲線グラフが用意されており、屈折度数や眼軸長の変化を一目で把握できます。
定期的な受診時に更新することで、近視の進行具合が「見える化」され、ご家族とも共有しやすくなります。
◆受診ごとの記録(7ページ以降)
毎回の受診時に以下の情報を記録します:
-
視力(裸眼・矯正)
-
近視度数(D)
-
眼軸長(記録可能な場合)
-
近業や屋外活動の時間
-
寝る時間や生活習慣の詳細
-
オルソケラトロジー、低濃度アトロピン点眼などの治療内容と期間
具体的な生活記録には次のような項目があります:
-
屋外活動時間:( )時間/日
-
書字・読書:( )時間/日、距離( )cm
-
スマホ・タブレット:( )時間/日、距離( )cm
-
パソコン:( )時間/日、距離( )cm
-
就寝時間:午後・午前( )時頃
まとめ:未来の視力を守るために
子どもの近視は早期発見・早期対応が極めて重要です。「視力の記録ノート」は、単なるメモではなく、保護者・医師・子ども本人が三者で視力の変化を把握し、よりよい生活習慣や治療選択につなげていくための『共通言語』となります。
当院では、このノートを活用することで、保護者の皆様と協力しながらお子様の視力を守る取り組みを進めてまいります。ご興味のある方は、ぜひご相談ください。
出典:
視力の記録ノート(監修:大野京子教授・東京科学大学)
参天製薬株式会社より配布
※ノート本体PDF:https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/myopia/pdf/vision_note.pdf




コメント