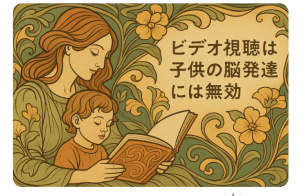 幼児のスクリーン曝露と注意力の発達:脳波研究が示す新たな警鐘
幼児のスクリーン曝露と注意力の発達:脳波研究が示す新たな警鐘
―ビデオでの学習は、幼児の注意力の発達に良い影響を与えられない可能性―
小児の脳の発達とSNS・デジタルデバイスの関係は、近年ますます大きな社会的関心を集めています。今日紹介する論文は2019年と少し古いものですが、幼児の「スクリーン曝露」が注意力や脳活動に与える基本的な影響を丁寧に検証した重要な基礎研究であり、現在の議論にもそのまま通じる価値を持っています。眼科医として、視覚の発達と脳の働きは不可分であるため、きわめて示唆的な内容と感じます。
この研究は、4〜6歳の幼児を対象に、6週間にわたり物語を“画面で見る場合”と“大人が読み聞かせる場合”で、注意力や脳の働きにどのような違いが生じるかを調べたものです。幼児期は視覚・注意・言語機能が急速に発達する時期であり、このような実験は発育中の脳が外界の刺激をどう受け取るかを理解する上で極めて重要です。
研究では幼児を二つのグループに分け、一方にはタブレットを用いた物語視聴、もう一方には大人による直接の読み聞かせを実施しました。介入前後で注意力テスト、保護者による評価、そして安静時の脳波(EEG)を測定し、とりわけ集中状態を示すベータ波と、ぼんやりした状態で強くなるシータ波の変化に注目しました。これらの比率は、注意障害の有無を推定する指標としても知られています。
結果として、読み聞かせを受けた幼児では注意力が向上した一方、スクリーン群では改善がみられませんでした。さらに脳波の解析では、スクリーン群の幼児においてシータ波が相対的に強く、ベータ波が弱いという「注意が維持されにくい脳活動パターン」が確認されました。これは注意障害の子どもにみられる波形に近く、幼児期のスクリーン曝露が注意ネットワークの発達を妨げる可能性を示唆します。保護者が「注意が散りやすい」と評価した子ほどシータ/ベータ比が高かったという点も、行動の特徴と脳活動が一致していることを示す重要な所見です。
読み聞かせには、視線の交わり、声の抑揚、表情、ページを指さす動作など、多様な“共同注意”の要素が自然に含まれます。これが脳の注意ネットワークを活性化し、視覚的・言語的な処理を統合的に促すため、幼児の発達に良い影響を与えるのだと考えられます。一方、スクリーン視聴は受動的になりやすく、光刺激が強く、視覚情報が速く切り替わるため、幼児の未熟な脳には過剰な刺激になり、落ち着いた注意の持続が育ちにくいのかもしれません。
眼科臨床の立場からも、視覚発達には“誰と、どう関わりながら見るか”が重要です。もっとも柔軟に発達する幼児期には、ビデオ視聴を長時間続けるより、読み聞かせや外遊び、親子の対話といった活動が、視覚・注意・認知の健全な基盤をつくります。スクリーンを完全に否定する必要はありませんが、短時間に区切る、親子で一緒に見て話しながら使うなど、使い方の工夫が不可欠です。
今回の研究は、幼児にとって“人から学ぶ時間”の価値を科学的に裏付ける重要な示唆を与えるものといえるでしょう。
出典:Zivan M, Bar S, Jing X, Hutton J, Farah R, Horowitz-Kraus T. Screen-exposure and altered brain activation related to attention in preschool children: An EEG study. Trends in Neuroscience and Education, 2019. DOI: 10.1016/j.tine.2019.100117




コメント