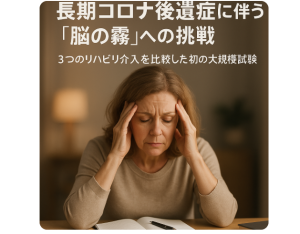 長期コロナ後遺症に伴う「脳の霧」への挑戦
長期コロナ後遺症に伴う「脳の霧」への挑戦
―3つのリハビリ介入を比較した初の大規模試験
新型コロナウイルス感染症が治った後も、集中力が続かない、物忘れが増えた、頭がぼんやりする――。こうした「脳の霧(ブレインフォグ)」と呼ばれる症状に悩む人が少なくありません。アメリカでは成人の約7%が長期にわたる新型コロナウイルス感染症(Long COVID)を経験しているとされ、その多くが日常生活や仕事に支障を感じています。しかし、これまで効果が確実に示された治療法はほとんどありませんでした。
研究の目的と背景
この研究は、米国国立衛生研究所(NIH)の「RECOVER」プロジェクトの一環として行われたもので、長期コロナの認知障害を改善するエビデンスに基づくリハビリ法を検証することを目的としました。研究チームは、22の医療施設で実施可能な3つの方法を選び、それぞれの有効性を比較しました。
研究方法
2023年8月から2024年6月にかけて、328人の参加者がオンラインで10週間の治療を受けました。平均年齢は48歳、約7割が女性でした。
参加者は次の5つのグループにランダムに分けられました。
-
BrainHQ:個々の能力に合わせて難易度が変わるオンライン認知トレーニング。
-
PASC-CoRE + BrainHQ:認知行動リハビリをグループ・個別で行い、さらにBrainHQを併用。
-
tDCS + BrainHQ:頭皮上から微弱な電流を流す「経頭蓋直流刺激(tDCS)」を加えた組み合わせ。
-
アクティブ比較群:パズルやゲームなどの非構造的コンピュータ課題。
-
偽tDCS + BrainHQ:tDCSの電流を流さないコントロール群。
いずれの介入も週5回、10週間継続され、治療前後で「日常生活の中での物忘れや注意力の変化(修正版ECog2スコア)」を自己評価する方式で比較されました。
結果
どの介入も、他の方法に比べて明確な改善効果は認められませんでした。
BrainHQ単独群、PASC-CoRE併用群、tDCS併用群のいずれも、アクティブ比較群と比べて有意差はなく、統計的に0.0〜0.1程度の小さな差しか見られませんでした。
ただし、全ての群で時間の経過とともに少しずつ改善がみられた点は注目されます。これは、自然回復や「訓練を受けている」という心理的効果が影響している可能性があります。副作用はほとんどなく、安全性は確認されました。
意味と今後の展望
この結果は、「現時点で有効と断言できるリハビリ法はない」という厳しい現実を示しています。一方で、こうした研究が体系的に進んだのは大きな前進です。認知機能障害の回復には、より長期的で個別化された支援が必要であり、神経可塑性(脳の再適応力)を活かす治療の開発が今後の課題とされます。
出典:
Nopman DS, Cortay D, Laskowitz D, et al.
Evaluation of Interventions for Cognitive Symptoms in Long COVID: A Randomized Clinical Trial.
JAMA Neurology, published online November 10, 2025. doi:10.1001/jamaneurol.2025.4415
清澤のコメント:若かりし頃、私はフランスで霊長類を用いて、当時アルツハイマー病などの原因病巣と疑われていた脳のマイネルト核障害と脳代謝の関係を解析する研究に加わったことがあります。その後、米国ではアルツハイマー病患者の脳糖代謝と視覚失認との関連を調べる臨床研究に加わりました。こうした経験から、現在も眼科医でありながら、認知症における視覚失認を含む認知障害に強い関心を持ち、日常の診療でもその観点を意識して患者さんに接しています。
その意味で、今回のJAMA Neurology誌の論文は、単に神経内科領域の話にとどまらず、私たち眼科医にとっても興味深い内容です。
本研究は「Long COVID(長期新型コロナ後遺症)」に伴う認知機能低下を対象とし、オンライン認知トレーニング、構造化された認知リハビリ、経頭蓋直流刺激といった3種の介入を厳密なランダム化臨床試験で比較したものです。結果としては、いずれの介入も統計的に有意な改善を示さなかったことが報告されました。この結果は「現時点では特定のリハビリ法に決定的な根拠はない」ことを意味しますが、一方で、時間の経過とともに全群で軽度の改善が見られた点は希望を感じさせます。これは、脳の可塑性や回復過程がゆっくりと進む可能性を示唆しているとも言えます。
眼科診療の現場でも、長期的なストレスや感染後の“脳疲労”を訴える方が増えており、視覚情報処理と認知の関係を改めて考えさせられます。
眼は脳の一部であり、「見る」という行為の背後には高度な認知処理があります。したがって、視覚失認のように“見えているのに理解できない”状態や、注意・集中力の低下による視覚疲労は、認知障害や脳代謝異常と密接に関連しています。
今後、Long COVID後の患者さんの「見え方の質」や「視覚認知の変化」にも注意を払いながら診療を続けていきたいと思います。
出典
Noppman D S, Cortay D, Laskowitz D et al.
Evaluation of Interventions for Cognitive Symptoms in Long-Term COVID-19: A Randomized Clinical Trial.
JAMA Neurology, Online November 10, 2025. doi: 10.1001/jamaneurol.2025.4415.




コメント