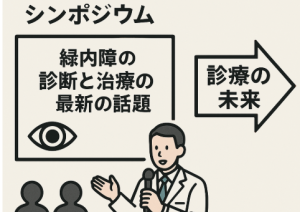 清澤のコメント:「国際シンポジウム 2: 緑内障診断のアップデートUpdates on Glaucoma Diagnostics」(2025年日本眼科学会4月19日開催)で話される各演者の発表内容を、抄録から4月11日時点でわかりやすくまとめます。講演内容は現在即利用できるものばかりではありませんが、現在までの眼底画像解析や視野計の進歩普及を見れば、今後もこの緑内障診断分野は急速な進展が予測されます。一方、その進歩に付いて行く努力をする医師と、努力の乏しい医師の差も開き、それも患者さん側から評価されることでしょう。
清澤のコメント:「国際シンポジウム 2: 緑内障診断のアップデートUpdates on Glaucoma Diagnostics」(2025年日本眼科学会4月19日開催)で話される各演者の発表内容を、抄録から4月11日時点でわかりやすくまとめます。講演内容は現在即利用できるものばかりではありませんが、現在までの眼底画像解析や視野計の進歩普及を見れば、今後もこの緑内障診断分野は急速な進展が予測されます。一方、その進歩に付いて行く努力をする医師と、努力の乏しい医師の差も開き、それも患者さん側から評価されることでしょう。
IS02-1 カーヴェ・マンスーリ(Kaweh Mansouri)
(スイス・ローザンヌSwiss Visio、コロラド大学)
「眼圧の連続モニタリングの最新情報」
マンスーリ先生は、眼内に小型センサーを入れて、24時間絶えず眼圧を記録できる革新的な方法について紹介しました。これにより、従来の診察室での一時的な眼圧測定では見逃されていた日中・夜間の変動が把握でき、手術後の眼圧の変化も詳しく追えるようになっています。将来的には、このようなセンサーによる連続モニタリングが、緑内障の診断や治療の質を高めると期待されています。
IS02-2 チョン・ジンウク(Jin Wook Jeoung)
(ソウル大学 医学部および病院)
「高精細画像とAIによる緑内障診断の進化」
チョン先生は、最先端の画像技術と人工知能(AI)を使って、視神経の微細な構造を詳細に観察する方法について解説しました。AIを活用することで、緑内障と正常な目、さらには他の視神経疾患との違いを高精度に判別できるようになっています。特に「適応光学OCT」や「層別解析」により、網膜の奥深い構造の可視化が進み、診断の早期化や個別治療が可能になると期待されています。
IS02-3 野本 裕貴(近畿大学)
「視野検査の進歩と新しい手法の紹介」
野本先生は、緑内障の進行を調べるために重要な視野検査について、従来の「自動視野計」の精度を保ちながら、検査時間を短縮する新しいアルゴリズムの進歩を紹介しました。さらに、タブレット端末を用いた新しい視野検査や、立体視を使った検査法にも触れ、患者の負担を減らしつつ、より正確な診断ができる未来の検査法について解説しました。
IS02-4 羽入田 明子(慶應義塾大学)
「緑内障の危険因子の最新知見」
羽入田先生は、緑内障を早期に発見し、予防するためにはリスク要因をよく知ることが重要だと述べました。眼圧の高さが唯一治療で改善できる要因である一方で、遺伝的な体質や生活習慣(睡眠、運動、食事など)も発症に関与しているとする大規模データ研究の成果を紹介しました。今後は、これらを踏まえた個別化されたリスク評価と生活改善指導が注目されると考えられています。
この国際シンポジウムでは、緑内障の診断と治療に関する最新の話題が多角的に紹介され、診療の未来を示唆する内容が満載で示されるでしょう。




コメント