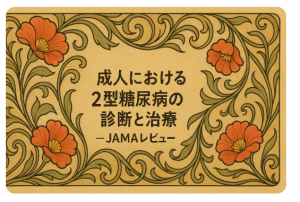 2型糖尿病は世界で急増し、心疾患・腎不全・失明など重大な合併症を招きます。診断は血糖値やHbA1cで行い、治療は生活習慣改善とメトホルミンが基本。心血管・腎リスク例にはSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を早期併用し、個別化治療で合併症予防とQOL向上を目指すことが重要とされます。
2型糖尿病は世界で急増し、心疾患・腎不全・失明など重大な合併症を招きます。診断は血糖値やHbA1cで行い、治療は生活習慣改善とメトホルミンが基本。心血管・腎リスク例にはSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を早期併用し、個別化治療で合併症予防とQOL向上を目指すことが重要とされます。
テーマ:成人における2型糖尿病の診断と治療 ― JAMAレビューから
背景
2型糖尿病は、膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンが徐々に不足し、かつ体の細胞がインスリンに反応しにくくなる(インスリン抵抗性)ことから生じる病気です。結果として血糖値が慢性的に高くなります。全世界の糖尿病患者の90〜95%を占め、その数は6億人以上と推定され、アメリカでは成人の6人に1人が罹患しています。心臓病、腎不全、失明などの合併症と強く関連するため、早期診断と適切な治療が重要です。
目的
今回のJAMAレビューは、成人における2型糖尿病の診断基準と、最新の治療戦略(生活習慣改善から薬物療法まで)を整理し、心血管・腎臓・視覚障害などの合併症予防にどのように役立つかをまとめることを目的としています。
方法
過去の大規模研究やランダム化比較試験、メタアナリシスの結果をもとに、診断基準、危険因子、治療法の効果が系統的に整理されました。特に血糖コントロールと合併症予防の関連、各種薬剤の心血管・腎臓への効果について詳細に検討されています。
結果
-
診断基準
-
空腹時血糖:126 mg/dL以上
-
HbA1c:6.5%以上
-
ブドウ糖負荷試験2時間値:200 mg/dL以上
-
-
危険因子
高齢、家族歴、肥満、運動不足、妊娠糖尿病の既往、アジア人・黒人・ヒスパニック系など特定の民族背景。 -
合併症の頻度
-
心血管疾患:約3分の1
-
視力障害・失明:10%超
-
腎不全:約40%に合併
-
-
生活習慣改善
-
体重管理は最重要。ただし特定の食事療法が他より優れている明確な証拠はない。
-
運動はHbA1cを0.4〜1.0%改善し、血圧や脂質異常も改善。
-
-
薬物治療
-
第一選択:メトホルミン
-
心疾患や腎疾患を伴う場合:GLP-1受容体作動薬(GLP-1RA)やSGLT2阻害薬(SGLT2i)を推奨
-
他の選択肢:DPP-4阻害薬、スルホニル尿素、チアゾリジンジオンなど
-
3分の1の患者は生涯でインスリン治療が必要
-
-
新しい知見
-
SGLT2iやGLP-1RAは心筋梗塞・心不全・腎疾患のリスクを20〜30%以上低下させる。
-
新しいGLP-1RAやGIP/GLP-1RAの二重作動薬は体重を5〜10%以上減らす効果もある。
-
結論
2型糖尿病は世界人口の最大14%に影響を与える深刻な疾患であり、心臓病、腎不全、失明などの合併症を予防することが極めて重要です。診断には血糖やHbA1cの基準を用い、治療ではまず食事・運動・体重管理といった生活習慣の改善が基本となります。そのうえで、メトホルミンを第一選択とし、心血管・腎リスクが高い場合にはSGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬を早期に組み合わせることが推奨されています。
👁️🗨️ 清澤院長コメント
2型糖尿病は眼科の現場でも非常に重要な病気です。糖尿病網膜症は失明原因の上位にあり、血糖コントロールの良否が眼の予後に直結します。今回のレビューは糖尿病治療の全体像を整理しており、内科的治療と眼科的フォローアップが協力して進められるべきことを改めて教えてくれます。
出典
Rita R. Kalyani, MHS; Joshua J. Neumiller, PharmD, CDCES; Nisa M. Maruthur, MHS, et al.
Diagnosis and Treatment of Type 2 Diabetes in Adults: A Review
JAMA. Online published June 23, 2025.
追記;これに関連したオーディオポドキャストの要約;
2型糖尿病の診断・治療指針の最新レビュー:
はじめに
2型糖尿病は世界の成人で非常に高頻度に発症し、心血管疾患・腎障害・網膜症などを引き起こします。診断基準や治療戦略が近年アップデートされ、早期発見・リスク分類・治療選択がより精緻になりました。今回は、JAMAに掲載された最新のレビューとポッドキャストをもとに要点を整理します。
診断:いつ・どのように
-
診断基準は以下のいずれかを満たせば確定:
-
空腹時血漿グルコース ≥126 mg/dL
-
HbA1c ≥6.5%
-
75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値 ≥200 mg/dL
-
-
リスク因子は肥満、身体活動不足、高齢、家族歴、妊娠糖尿病の既往、特定人種(アジア系・黒人・ヒスパニックなど)。
-
診断時点で既に心血管疾患・腎機能障害・網膜症を伴う例も少なくありません。
治療の柱:生活習慣+薬物療法
生活習慣の介入
-
減量、食事療法、運動習慣が基盤。HbA1cを0.4〜1.0%改善させる効果が報告されています。
-
特に肥満例では体重減少により微小血管合併症の進行抑制も期待できます。
薬物療法
-
第一選択薬はメトホルミン。
-
心血管疾患・腎疾患を有するかリスクが高い場合は、GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬を早期に併用。これらは心血管イベントや腎障害進展を防ぐ効果があります。
-
他の選択肢にはGIP/GLP-1複合薬、DPP-4阻害薬、スルホニルウレアなど。
-
インスリンは全体の約3分の1の患者が生涯のどこかで必要とし、特に診断初期で著しい高血糖や代謝失調がある場合は導入を検討。
合併症予防と眼科の視点
-
HbA1cの厳格な管理は網膜症・腎症といった微小血管合併症の予防につながることが証明されています。
-
糖尿病診断後は速やかに眼科受診を行い、定期的な眼底検査を続けることが推奨されます。
-
内科的治療と眼科的管理の連携が、失明予防の観点からも欠かせません。
個別化医療の重要性
-
年齢・合併疾患・体重・低血糖リスクを考慮し、HbA1c目標と治療強度を調整。
-
特に心血管疾患や腎疾患を持つ患者では、GLP-1 RAやSGLT2iの選択が生命予後とQOL改善に直結します。
結び
-
2型糖尿病は血糖コントロールと生活習慣改善が基本。
-
メトホルミンを基盤としつつ、心血管・腎・網膜症リスクに応じて薬剤を追加。
-
眼科領域では網膜症予防のため、診断時からの厳格な血糖管理と定期検査が不可欠です。
出典
-
Kalyani RR, Neumiller JJ, Mamtani N, et al. Diagnosis and Treatment of Type 2 Diabetes in Adults: A Review. JAMA. 2025;333(24):2339-2352. doi:10.1001/jama.2025.2362
-
JAMA Clinical Reviews Podcast: Type 2 Diabetes: Diagnosis and Current Guidelines for Treatment
-




コメント