教育セミナー5「斜視の病因・病態の新しい理解」
日時:2025年4月18日(金) 9:00〜10:20 第4会場
オルガナイザー:佐藤美保(浜松医科大学)、根岸貴志(順天堂大学)
オルガナイザーの佐藤美保先生と根岸貴志先生は、年齢ごとに異なる病態を持つ斜視の理解を深める目的で本セミナーを企画した。近年の研究で斜視の病因解明が進んでおり、乳幼児・若年者・高齢者のそれぞれに特有の疾患と対応を学ぶことで、診療の質を高められるとした。
E05-1 横山吉美(JCHO中京病院)
「立体視発達期である乳幼児期の斜視にどのように対応すべきか」
乳幼児の斜視治療では、視力の改善だけでなく立体視の獲得が重要である。特に乳児内斜視は従来、立体視の獲得が困難とされたが、超早期手術による良好な眼位の維持がカギとなりうることが、国内外の報告から明らかになっている。調節性内斜視の早期発症例や、乳児期の外斜視、上斜筋麻痺も対象とし、眼鏡による完全屈折矯正の意義や早期受診の重要性を解説。立体視は運動能力や社会生活にも大きく影響するとし、早期介入の啓発を訴えた。
E05-2 飯森宏仁(愛媛大学)
「若年者の後天共同性内斜視とデジタルデバイスの関連」
近年若年者に急増する急性後天共同性内斜視(AACE)について、スマートフォンなどデジタルデバイスの長時間使用との関連が注目されている。これを検証すべく、日本弱視斜視学会と日本小児眼科学会の共同でACE-DD Studyが実施され、発症1年以内の5~35歳の患者を対象に、**屈折矯正とデバイス使用の制限(距離30cm以上、定期的休憩)**を行い3か月経過を追った。AACEの診断と治療のポイントを解説するとともに、日常診療での生活指導の重要性を強調した。
注:AACE
E05-3 國見敬子(神奈川歯科大学・北里大学)
「眼窩プリー障害による斜視疾患 -Pulley degeneration disorders-」
眼窩プリーの脆弱化によるSagging Eye症候群(SES)や、強度近視性内斜視を取り上げた。SESは加齢に伴い増加する後天的斜視の一因で、sagging-like face、遠見内斜視、小角度斜視が特徴。一方、強度近視性内斜視はアジア人に多く、大角度の内斜視・下斜視を呈する。鑑別には脱臼角の測定(120度以上)が有用。治療は軽症例には両眼倍量内直筋後転術、重症例やHeavy Eye症候群(HES)には横山法が推奨される。非専門医でも対応可能な診療指針として整理された。
オルガナイザーコメント(再掲)
佐藤美保先生は、「斜視診療では年齢層ごとの疾患特性を知ることが、患者初診時の適切な対応につながる」と述べた。根岸貴志先生も、「スマホ斜視や高齢者の複視といった新たな病態に対して、病因解明に基づく対処が求められる」として、セミナーの意義を強調した。

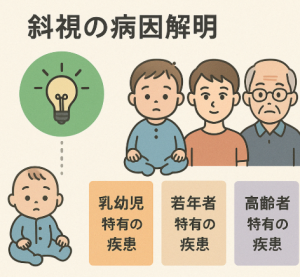



コメント