目隠しをして食事をすると、摂取カロリーが25%減る!? 舌だけで感じられる「純粋な味」はない。眼や耳から得た情報を合わせて「味」ができる (婦人公論.jp) – Yahoo!ニュース

舌だけで感じられる「純粋な味」はない。目隠しをして食事をすると、摂取カロリーが25%減る!? 舌だけで感じられる「純粋な味」はない。眼や耳から得た情報を合わせて「味」ができる
清澤のコメント:今日の目と視覚の話題は、舌だけで感じられる「純粋な味」はないというお話です。私たちは「美味しさ」をどのように判断しているのでしょうか――複数の感覚モダリティーは独立して存在してはいない
8/30(火) 12:31配信
上記記事の抄出採録です:
「美味しい」と感じる日々の食事。しかし、その「美味しさ」は舌だけで決まるものではなく、見た目や咀嚼音なども影響しています。九州大学大学院比較社会文化研究院講師の源河先生によれば、「味覚のみで感じられ、かつ、他から影響を受けない〈純粋な味〉などない」とのこと。たとえば、目隠しをして食事をすると、通常よりも少ない摂取カロリーになるそうで――。 * * * * * * *
◆聴覚の場合、音を大きく高くしたときにパリパリさが増すように錯覚するのは納得できる。これに対し視覚の場合、なぜ丸かったり赤かったりする方がより甘く感じられるのだろうか。 視覚から味への影響には期待や知識が重要な役割を果たしていると言われる。甘いものは丸いことが多い。私たちは丸さと甘さを両方もつものを何度も食べているうちに、丸いものは甘いという期待を抱くようになってしまっている。そのため、丸い食べ物を見ると甘いのではないかと期待され、その期待が影響してより甘いと思ってしまうというのだ。 同様に、熟した果物は赤くて甘いが、熟してない果物は甘くなく青や緑であるという経験則を身につけていると、赤いものを見たときに甘さが期待されるのだ。
◆着色された白ワインに気づけなかった理由:ワインの場合には注意も関与しているだろう。ワインの専門家は、ワインのどこに注意を向ければそのワインらしい特徴を把握できるか、その注意の向け方を熟知している。 そして、ワインを区別するための手がかりとして色についての視覚情報も利用される。こうした視覚情報は、ワインを口に入れる前の段階で味覚の注意を方向づけるだろう。たとえ口のなかに白ワインが入っていても、白ワインらしい特徴に注意が向かなくなってしまう。赤く着色した白ワインを赤ワインのように感じてしまった間違いは、視覚情報を利用する訓練をしてきた専門家だからこそ起きてしまったものなのである。 ここまで、飲食物の見た目を変えると味が変わるという錯覚をいくつか紹介した。こうした錯覚は、通常ならうまくいく規則が特殊な条件のもとで使われていることを示している。錯覚でない場面でも、眼や耳で捉えた情報は舌で捉えた情報と統合され、私たちが普段「味」と呼ぶものができあがっているのだ。 だが、以上の議論を読んでも、眼や耳の影響を否定したい人がいるかもしれない。そうした人は眼と耳をふさいで感じられるものこそ「本来の味」だと言うだろう。最後に、こうした人に対するダメ押しを述べておこう。
◆「本来の味」は眼と耳を塞いだら得られる? 2000年代のはじめ、暗闇のなかで料理を食べる「ブラインド・レストラン」というものがあったが、そこに来た客は普通のレストランよりも少ない量しか食べなかったという。また、目隠しをして食事をする実験では、普段より25パーセントほど摂取カロリーが少なかったそうだ。暗闇のなかでは食べる量だけでなく味やおいしさの感じ方が変化してしまうことを示す実験もいくつかある。 こうした変化の原因は、まさに見えないことにあるだろう。食べているものが見えないと、何を食べているか不安に思ってしまい、安心して口に運ぶことができないのだ。もちろん、レストランに来た客も実験の参加者も、レストランや実験で危ないものを食べさせられるはずはないと確信できている。それでも、見えないことで食べる量や感じられる味に影響が出てしまうのだ。 この例からわかるのは、視覚の遮断そのものが味に影響を与えてしまうということである。目隠しをすれば視覚の影響を排除した「純粋な味」が感じられるようになるわけではない。食べ物が見えないときに感じられるのは、拭えない不安を帯びた味なのだ。聴覚にも同じことが言えるだろう。 そうすると、目隠しや耳栓をして感じられる味は口のなかで働く感覚(味覚・嗅覚・触覚)だけで感じられた「味そのもの」ではないことがわかる。そこで感じられているのは、通常なら眼や耳を使って得られた情報が欠如した、情報の少なさによる不安に影響された味なのである。
◆味覚だけで感じる「純粋な味」はない: 以上からすると、舌ないし味覚のみで感じられ、かつ、他から影響を受けない「純粋な味」などありそうにない。多感覚知覚は私たちの知覚システムが自動的に行っているものであり、それぞれの感覚が得た情報は私たちの意志とは独立に勝手に統合されてしまう。いくら努力しても、味覚だけに集中して食べ物を味わうことは不可能なのである。 確かに、味覚だけが働いている状況というものは理解できる。それぞれの感覚には対応する神経システムがあり、ある感覚が働かなくなっても別の感覚まで働かなくなるわけではないからだ。 視覚に関わる神経システム(眼球、網膜、視神経、脳の視覚野)が何らかの理由で働かなくなったとしても、聴覚システム( 鼓膜、蝸牛(かぎゅう)、聴覚神経、聴覚野など)は働き続け、依然として音は聞こえるだろう。同様に、味覚以外が失われ、他の感覚から独立して味覚が単独で捉えた味が感じられる状況があると理解することができるように思われる。 だが、そこで感じられる味を私たちは本当に想像できているのだろうか。風邪をひいて鼻が詰まっただけで味がよくわからなくなるのに、見た目も咀嚼音も感触も温度もともなわない味がどんなものか本当に思い浮かべられるだろうか。 かりに想像できたとしても、そうした「純粋な味」は、私たちが普段の生活のなかで「味」と呼んでいるものとは大きく異なっているだろう。私たちが普段経験する味、そして、「味とはこういうものだ」という日常的な味概念は、五感で感じられた味をもとに作られている。ポテトチップスの味は、その色や噛んだときの音を含めたものとして理解されているのだ。
※『「美味しい」とは何か――食からひもとく美学入門』(中公新書)の一部を再編集したものから短縮です。


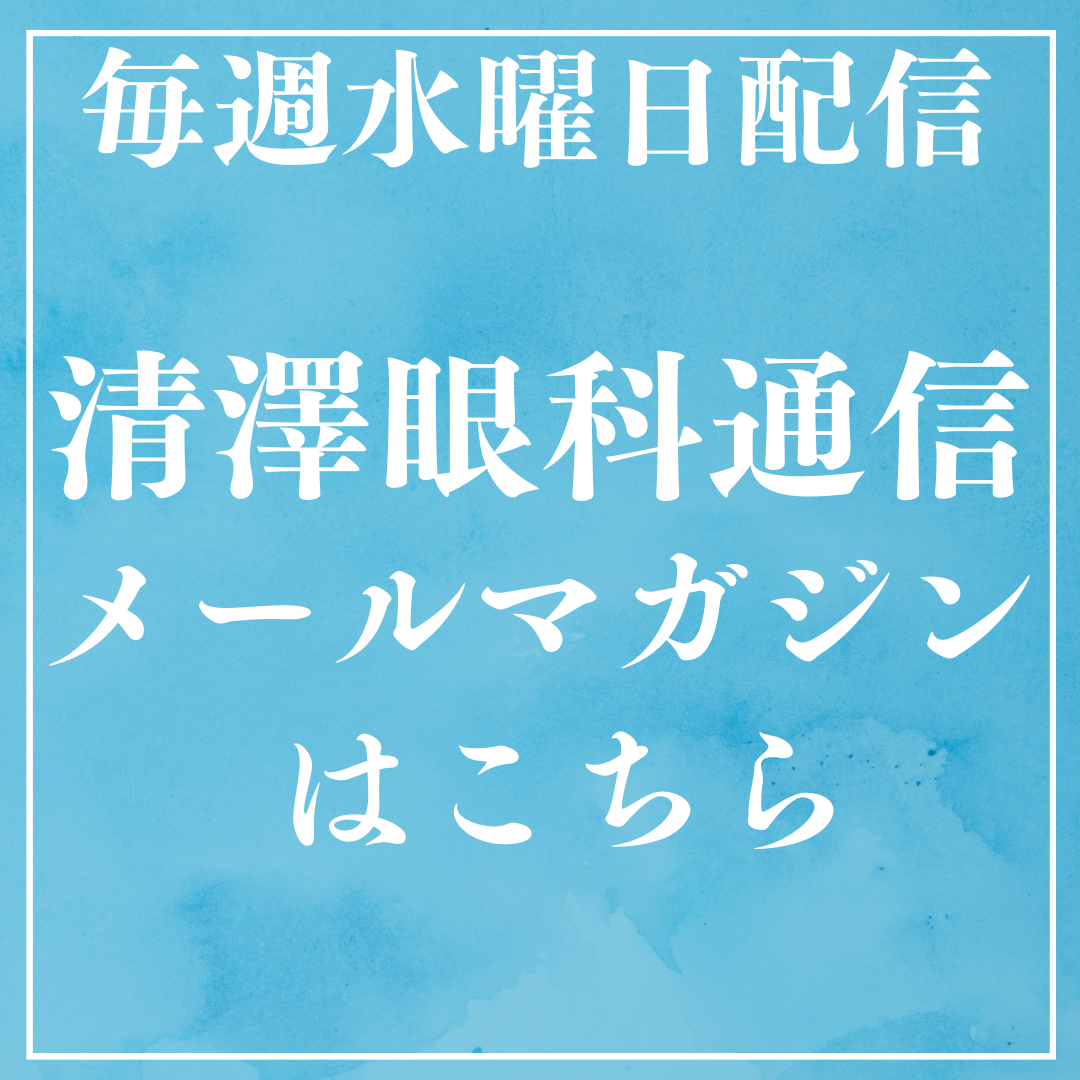

コメント